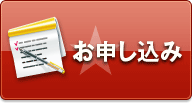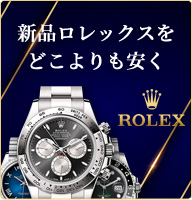決算の早期化のプロセスは、具体的には経理業務を中心とした業務フローの見直しや、組織体制の見直し、月次決算の精度向上の効果をもたらしました。当初は上場企業や連結会計を扱う大企業が主な対象でしたが、そのプロセスについては、規模の大小を問わず、業務効率化の一つとして浸透してきました。
少し目線を変え、「経営者の目線」から決算の早期化を考えてみましょう。経営者の目線で考えると決算情報がいち早く欲しいのは「月次決算」です。
1 決算早期化とは
「決算の早期化」とは、決算処理を早期に実施することを意味しています。今期の決算日が経過したら速やかに決算資料を作成するということです。
この言葉が使われ始めたのはおよそ20年ほど前からです。
1990年代において、決算の早期化の背景にあったのは、連結決算の早期公開でした。1992年以降、グループ連結決算が有価証券報告書の本体に組み込まれ、開示内容も拡大されてゆきました。株主や投資家に対する決算情報として連結財務諸表の重要性が増してゆくなか、連結決算と単体決算を同時発表するために、主に連結決算処理プロセスの短縮に取り組む企業が増えました。
2000年代以降は、有価証券報告書の記載方法が、連結財務諸表が先で個別財務諸表が後、と変更になり、一層連結財務諸表の早期作成について重要性が増しました。また証券取引所も決算後30日以内に決算発表する会社を「早期決算会社」と発表し推奨しました。決算後速やかに決算発表する会社は、投資家に対し情報開示を積極的に行う企業であり、市場の透明性や、投資家保護の立場を図りたい証券取引所にとっても、決算の早期化は推進したいテーマでした。実際にこうした動きの中、30日以内に早期に決算を発表する会社は順調に増加しました。
2010年代以降は、国際的な会計基準である「IFRS(国際財務報告基準)」の対応として、海外の子会社を含めた連結会計への取り組みが求められています。グループ全体での決算処理が求められる中で、早期処理に加え、決算処理プロセスの統一や、標準化がテーマとなる企業が増えています。
こうしてみると決算の早期化は、有価証券報告書や会計制度の変更を契機に、主に投資家や株主を対象として拡大をしてきていることがわかります。とくに急速に進展した企業のグローバル化に伴う会計制度の対応としてきたものであると言えます。
2 経営情報としての月次決算
通常、会社の決算は年1回というところが多いですが、出来上がった決算書を見て、初めて会社の状況を把握するのでは、スピーディな経営判断は到底できません。決算書が納税額を計算するためだけの決算書であれば、年1回出来上がったものを見ればよいですが、決算資料の持つ情報の意味はそれだけではありません。
2-1 月次決算の目的
本決算は1年間の企業活動の内容をまとめ、貸借対照表や損益計算書を作成し、法人税や消費税などの納税をするものです。
月次決算は1ヶ月間の活動内容を記録してゆきます。予算計画に対し進捗率が確認できるため、経営者としては正しい経営判断の基礎となるデータであり、次に打つ対策を検討する際には必要なデータです。金融機関とのやりとりの中でも月次決算内容を報告するケースが多くあります。
月次決算の目的は以下の4つです。
- ①経営状態の把握と対策の実行
- ②年度計画の進捗管理
- ③年次決算の着地見込
- ④年次決算に備えたデータ整備
①経営状態の早期の把握と対策の実行
経営者の知りたい決算情報とは、会社の現状が正確に把握でき、次の対策を打つための大切な情報です。「今期は調子がいい」「この商品は売れていないな」だけでは、会社の姿は見えません。売上の増減だけでなく、原価率は上がっていないか、在庫は急激に増えていないか、間接経費は増えていないかなど、幅広いデータを集めてようやく、会社の全容を把握し、利益がコンスタントに計上できているかを確認します。
在庫が増えていれば、適正な水準に修正させます。仕入単価が上がっていれば、取引先と条件交渉をします。そうした指示を1年単位ではなく、1ヵ月単位で細かく軌道修正を行いながら経営を行ってゆくのです。
②年度計画の進捗管理
年度の売上計画や利益計画の達成率や進捗状況の管理を行います。部門別・商品別に分け、さらに細かい分析を行い、必要に応じ新たな対策を検討します。
③年次決算の着地見込
投資家や株主に対して今期の着地見込の最新情報を提供します。また金融機関に対しても定期的に着地見込を共有し、今後の資金調達や安定的な支援に繋げてゆきます。
④年次決算に備えたデータ整備
月次決算を毎月締めてゆくことで、年次決算時の見直し範囲を減らすことができます。またミスがあっても早期に発見することができるため、月次で決算処理を締めておく必要があります。
2-2 月次決算の早期化
月次決算をさらに有効に機能させるためにも、月次決算資料は速やかに作成する必要があります。業種によっても異なりますが月初5~10日程度で出せるようにしたいものです。
月次決算資料ができるのに半月かかっていると、日々の業務の軌道修正をしても、その効果が発揮される期間は当月では半月しかありません。5日前後で現状を把握し、速やかに軌道修正をすれば残り25日その効果を発揮することができます。スピーディな経営判断を行うには、月次決算を素早く作成する必要があります。
また、会計データのみではなく「単価」「延べ利用者数」「歩留まり率」など、各種経営指標を組み合わせながら、会社の状態を定点で観測してゆきます。
2-3 月次決算の早期化のメリット
月次決算を早期に作成することの効果は、以下の通りです。
- ①予算計画の進捗が確認できる
- ②現状把握と対策の検討が速やかにできる
- ③異常値の管理ができる
- ④資金繰り表作成の基礎データとなる
①予算の進捗率が速やかに確認できる
予算の進捗率が速やかに確認できるため、年度計画に対して順調に推移しているか否かが確認できます。月初速やかにデータが揃うことで、月の上旬から軌道修正を行うことができます。
②現状把握と対策の検討が速やかにできる
財務データと、会社の経営データ(客数、単価、従業員数など)と組み合わせることで会社の現状把握を行うことができます。必要に応じ対策を打っていくという、経営者が経営判断を行うための基礎データとして、大切な情報です。月単位でPDCAを回してゆくためには月初から対策に取り組み、翌月に検証できる体制を目指したいです。
③異常値の管理ができる
各勘定科目の増減を、前年同月比や前月比と比較することや、同業他社と比較することで異常値の把握ができます。事務のミスによるものか、一過性のものなのか、原因を把握し必要な対策を立てます。早期に発見することでミスの影響を最小限に抑えることができます。
④資金繰り表作成の基礎データとなる
月次の資金繰り表を作成する基礎データとなり、月中、月末から翌月の資金繰りを検討し、必要により資金調達の準備を進めます。
3 月次決算を早期化するには
それでは、具体的に月次決算を早期化するためにはどのような取組が必要でしょうか。
ポイントは業務改善です。
月次決算資料ができるまでの工程を見直し、無駄を省き、プロセスを工夫しながら改善を進めます。最初から100点満点のものはできませんが、PDCAを回しながら、業務改善を前に進めてゆきます。
またボトルネックになっている工程を洗い出します。例えば請求書の到着が遅れるために全体の工程に遅れが出る、承認者の出張が多く手続きが進まない場合などです。
3-1 現状の業務の棚卸
「月次決算を5日以内に作成する」という目標を決めた場合、まずは現状の業務フローを棚卸し分析します。一般的には以下のようなフローで月次決算が行われます。
①月末残高の突合
現預金は金庫にあるものを含め月末に必ず突合をします
↓
②月次棚卸
月末時点の在庫金額を確認します。期中の棚卸は簡略化して行う場合もあります
↓
③仮勘定の整理
仮払金や仮受金などは正式な勘定科目に振り替えます
↓
④経過勘定の処理
未払金・前払費用を計上します。期中の経過勘定は数が多数の場合もあり、
勘定処理の基準を事前に定めておきましょう。
取引先からの請求書や営業からの伝票が揃っていないと処理ができない場合がありますので締切日や処理ルールの徹底を図りましょう。
これは、レイアウト P タグのコンテンツです
⑤年間費用等の按分
年1回計上 減価償却、退職金給付費用、生命保険
年2回計上 賞与
年4回計上 固定資産税
↓
⑥月次試算表
↓
⑦月次業績報告
予算対比や前年同月比、前月比など経営判断に必要な項目を含んだ資料を作成します
各々の工程の締切日や処理に何日かかっているかを記録してゆきます。また誰がその工程を管理して、誰が関係者なのかも記録します。
3-2 業務プロセスの見直し
月次決算資料の報告を5日という目標を決めると、今度は日程を逆算してゆきながら、あるべき姿を話し合います。月末から始めるというよりは、月中にいかに段取りしておくかがポイントです。また社内社外を含めて、事務処理の締切日やルールを守らせるための呼びかけとチェックが必要になります。
同時並行で進められるものや、前工程からのデータ資料の提出が必要なものと整理して進めてゆきます。
3-3 ボトルネックの洗い出し
業務プロセスを見直すにあたり「何故時間がかかっているのか」を分析します。
主に要因別に分けると以下のようになります。
- 社外要因 取引先から請求書の到着が遅い
- 社内要因 営業からの請求書到着が遅い、社内の経費精算所の遅れ
- 部署内要因 伝票の起票作業が集中する、入力作業が集中する、手書きの作業が多い、キャッシュレス化が進んでいない、業務が属人的
- 組織体制 営業と経理との共有ツールが少ない 社内の伝達が遅い 承認の数が多い 決算の早期化に対する意識が低い
3-4 業務の平準化
業務分担を見直すと、例えば特定の人物に一定の期間あらゆる情報が集中する場合があります。その人が別業務やトラブルで時間を取られると、月次決算業務がストップしてしまいます。
そうならないためにも
- 他の人に任せる
- できる人を育てる
- 権限を委譲して管理スパンを変更する(判断が必要なものと不要なもの)
- 月内にできる処理を進めておく
- 業務の判断基準を明確にする(マニュアルの整備)
- システム化できるものは積極的に対応する
決算の時期に慌てて手続きを行うのではなく、事前に進めておいてピークの時期の山をなだらかにしておくことも必要です。経理部のみならず他の部署からの伝票締め切り日の厳守や、項目の見直しなど会社全体で業務プロセス改善の動きに巻き込んでゆく必要があります。
4 経理部の果たすべき役割
最後に決算の早期化を、従業員の側から考えてみます。
決算の早期化を考えるうえで、経理部の果たす役割は重要です。経理部はこれまでは、仕分けを行い、記帳処理を行うなどの事務処理を正しく行うのが、主なミッションでありました。決算の早期化を考えるなかで、特に月次決算の早期化というテーマにおいては「経営判断に必要なデータを速やかに作成する業務」です。今後の会社がどのような経営を行うのか、これまでの経営施策が有効に機能しているのかを検証する重要な役割を果たします。
決算の早期化の取組を通して、業務改善やひとつひとつの数字や手続きの持つ意味を改めて認識して、業務に対するモチベーションを高める機会とすることもできます。
5 資金移動を伴わずにできる節税対策
法人税は、会社が得た所得に対して課されます。会社がたくさんの利益を挙げることは喜ばしいことですが、その年の利益が多ければ多いほど、収める税金も高くなります。そこで、とくに中小企業の経営者などは、節税対策に頭を悩ませます。
節税対策は、基本的に、早めに手を打っておくことが重要です。とくに節税対策として効果的な役員報酬などは、期中に変更しても節税対策にはなりませんので、期初に決めておかなければなりません。また、期初に掲げた利益目標の進捗率は、毎月、もしくは四半期に1回くらいのペースで確認し、最終的な利益がどのくらいになるかを把握しておくことが大切です。それによって、効果的な節税対策を講じることもできます。
本決算の時期に利益が出そうだからといって、慌てて節税対策を打とうとしても、やることは限られてきます。それでも決算期になって、思わぬ利益が出ていることがわかったり、予想以上に納税額が多くなりそうなことが明らかになったりした場合はどうしたらよいでしょうか? そんなときに、少しでも利益を圧縮して節税できる方法をお教えします。
会社は、決算から2カ月以内に決算書・申告書を作成し、税務署に提出しなければなりません。その際、決算を終えて思わぬ利益が出ていることがわかったら、決算書の提出前に、何らかの節税対策を打ちたいところです。
しかし、すでに帳簿の整理や棚卸しなどを経て、決算は終わってしまっていますから、資金の移動を伴う節税対策はもう打てません。では、資金移動を伴わずにできる節税対策には、どのようなものがあるでしょうか。いくつかのケースを見ていきましょう。
5-1 未払金・未払費用の計上
5-1-1 請求額が確定していない修繕費
未払金と未払費用はよく似た勘定科目ですが、わかりやすく言うと、請求書が届いているのにお金を払っていないのが「未払金」、まだ請求書が届いていないが費用が発生しているものが「未払い費用」です。
たとえば、電話やインターネットなどの利用料金の計算期間が、月初めからでなく、前月の15日から翌月の15日だったとします。その場合、月末の決算日にも、料金は発生しています。そうなると、3月末決算の場合、3月分の料金の請求書が届くのは4月15日以降になりますから、これは「まだ請求書が届いていないが費用は発生している」ということで、「未払費用」になります。
この未払金や未払費用が、決算後の節税に役立つことがあります。たとえば、「修繕費」という費用科目があります。これは、工場の機械類や社用車、オフィスのパソコンやOA機器類、店舗や社屋などの建築物を修繕したり、メンテナンスしたりすることで、原状回復するためにかかる費用のことです。
こうした修繕工事を行い、決算日までに工事は終了したものの、請求額が確定していないというケースがあります。その場合、決算書・申告書の提出期限までに請求額が確定すれば、その金額を今期の経費として未払計上することができます。もし申告期限までに請求額が確定していなくても、工事を行った業者から、信ぴょう性のある見積金額を提示してもらえば、その金額を未払計上することが可能です。
5-1-2 その他の未払金・未払費用
修繕費以外にも、未払金や未払費用に当たるものがあります。
①給料(役員報酬を除く)
給料が20日締めで月末払いの会社の場合、決算日が月末であれば、21日から31日までの給料は未払計上することができます(ただし、この場合、後述するように、役員報酬は除きます)。
②光熱費、通信費など
電気代や水道代などの光熱費、電話代、インターネットの利用料金なども、料金の計算期間が月初めからでなく、前月の15日から翌月の15日など、月をまたぐことがよくある経費です。その場合、決算日が月末であれば、翌月15日までの料金を未払計上することが可能です。
③社会保険料
社会保険料は、通常1カ月遅れで預金口座から引き落とされ、納付します。そのため、多くの場合は、当月分の給与から前月分の社会保険料を支払っている形になっています。
例えば3月決算の場合、3月分の社会保険料と会社負担分と従業員負担分は、合わせて4月末日に預金口座から引き落とされます。つまり、3月分の社会保険料が決算日以降の支払になるため、この会社負担分の社会保険料を未払計上することができます。さらに、決算末日が土日や祝日の場合は、4月1日に支払われることになりますので、2カ月分の未払い費用を計上できます。
ちなみに、社会保険料の会社負担分とは、健康保険料と厚生年金保険料を折半した金額と、児童手当拠出金の合計額のことで、会計上、これらは未払費用(または福利厚生費)の勘定科目で計上します。一方、社員負担分は、「預り金」という形で計上します。
もっとも、これら①~③の未払金、未払費用は、すでに決算時点で経費として計上することがわかっているものだと思います。そのため、厳密にいえば節税というより未払金を経費として計上したかどうかを確認する作業ということになります。もし決算日までに支払事由が発生していたり、債務として確定していたりするのに未払となっているものを見つけたら、未払金や未払費用として計上することで、利益を圧縮して節税することができます。
5-1-3 該当すれば未払費用になるもの
次は、該当する会社は未払費用が計上できるものについて説明していきます。あくまでも該当する会社のケースであり、すべての会社に当てはまるわけではありません。
①固定資産税の未払計上
固定資産税とは、その会社の所有する土地や建物、機械など、文字通り固定資産にかかる税金です。この固定資産は、その年の1月1日時点の所有者に対して課税されます。そして、会計上は「租税公課」として経費処理することができます。
固定資産税の経費計上時期は、法人税基本通達によって、次のように決められています。
- A. 実際に納付した事業年度
- B. 納期の開始日の事業年度
- C. 賦課決定のあった事業年度(原則)
一般的には、経理処理を簡単に済ませるために、多くの会社はAを選択しています。
しかし、節税を考える場合は、Cを選択すると良いでしょう。賦課決定とは、わかりやすく言えば、納税通知書が届いた日です。納税通知書は届いているが、まだ納付が済んでいない分の固定資産税については、未払計上できます。
納税通知書は毎年4月頃に届きます。その通知書に基づいて、固定資産税は、4月、7月、12月、翌年2月の4回に分けて納付することになります(東京の場合は、6月、9月、12月、翌年2月)。
たとえば、これは数少ない例かもしれませんが、5月決算の会社の場合は、前月の4月に納税通知書が届きますので、7月、12月、翌年2月分の固定資産税を未払計上できるということです。
5-2 減価償却資産の取得
決算期などには、よく「固定資産の減価償却」という言葉を聞くと思います。これは、固定資産の経費計上の方法の一つです。
例えば、会社で使っている30万円以上の機械や備品などの固定資産は、購入した年に全額を経費として計上することはできません。その代わり、経費は何年かに分けて計上していきます。これが減価償却です。
減価償却が必要な資産は、法定耐用年数によって償却期間が決められています。例えば社用車やパソコン(サーバー用以外のもの)は4年、事務机は15年といった感じです。そのほか、建物や機械装置、工具、器具装備、特許権、営業権なども減価償却の対象になります。
この減価償却ですが、次の2つのケースについては、費用計上の時期を早めることができます。
①30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)
資本金額1億円以下の法人など、いわゆる中小企業は、30万円未満で購入した減価償却資産を、取得した年度に全額経費にすることができます。これを少額減価償却資産といい、中小企業だけに認められている特例です。ただし、その前提として、青色申告の届出をしていなければなりません。また、この場合、一括両脚できる資産は、合計で年間300万円までという限度額があります。
②一括減価償却資産
10万円以上20万円未満の減価償却資産については、個別に減価償却をせずに、一括減価償却資産として、使用した年から3年間で均等償却することができます。つまり、取得価額の合計額の3分の1を、毎年必要経費として計上していくのです。これは、大企業、中小企業など会社の規模には関係なく、また、限度額もありません。
このように、耐用年数が長い減価償却資産については、少額減価償却資産や一括償却資産として処理することで、費用計上のタイミングを早めることができます。
6 今期の決算に向けての節税対策も考えておく
このように、決算後にも行える節税対策はいくつかありますが、やはり決算期に利益が多すぎて慌てることがないように、今期の節税対策も講じておかなければなりません。
その際、節税対策として大きな効果を持つのが、会社が役員に支払う役員報酬です。これは、本来は税制上経費と認められていないものですが、一定の条件を満たせば、非課税にすることができます。
一定の条件とは、次のような場合です。
- ①定期同額給与
- ②事前確定届出給与
- ③利益連動給与
このうち②③は条件が厳しく、導入する手間暇が煩雑なため、①の「定額同時給付」について説明します。
役員報酬が定期同額給与とみなされるためには、1年間同額の月給が支払われなければなりません。逆に言えば、期中の役員給与の増減はできせん。増減すること自体は可能なのですが、正当な理由なく金額を変更すると、役員報酬のうち「定期同額」とはならない部分については、損金として認められません。
例えば、期の途中で報酬を月40万から60万に引き上げた場合も、月60万から40万に引き下げた場合も、経費として計上できるのは、月30万円までです。
役員報酬が少なくなると、実際の会社の所得以上の金額を基準にして、法人税の額が計算されます。また、法人税が増えるだけでなく、役員の住民税が増えることもあります。したがって、この役員報酬をいくらに設定するかということは、節税対策としては重要事項とも言えるのです。
役員報酬は、期中に変更すると、定期同額にならない部分については、損金として認められないと説明しましたが、事業年度開始から3カ月以内であれば、役員報酬の改定ができます。株式会社の場合であれば、役員報酬の支給額を最終的に決定するのは株主総会です。3月決算の会社であれば、3月末の決算日から6月の株主総会までの間に、改定も含め、支給額を決定します。
そこで、節税を考えて適切な役員報酬を決定するためには、今期の利益をある程度正確に予想することが必要です。そもそもの予想が赤字であれば、節税対策にそれほど頭を悩ませることもありませんし、もし利益がたくさん出そうだと予想される場合は、それに合わせて役員報酬も高めに設定しておくといいでしょう。
ただし、役員報酬を単純に引き上げると、こんどはそれを受け取る役員の所得税が引き上げられ、結果的に税金を多く払わなければならないケースも出てきます。それについてはここでは詳しく述べませんが、法人税の節税と併せて役員の所得税のバランスを考えながら、役員報酬を決めるのがいいでしょう。
7 決算書は作成した後どうなる?
決算書は作成した後は、一体どうなるのでしょうか。
また決算書の使いみちは様々ありますが、そもそも、決算書が有効なものとなるためには何が必要条件なのでしょうか。
このような疑問を解くカギの一つとして、株主総会の存在があります。そもそも決算書は株主に対して、経営者が経営状況などを説明するために作成するもの、という一面があります。
そうなると、株主総会に決算書を提出するということになるわけですが、次に疑問に思うのが、その場で株主は何をするのか、ということです。すなわち、提出された決算書を承認、つまり正式なものとして認めるという役割を担っているのか、あるいは、単に報告として受けるだけなのか、これは大きな違いです。
また、決算書を利用する金融機関など株主以外の立場からすると、株主総会の承認を得ていない決算書というものが存在するならば、それは正しいものとして利用して良いものか気になるところでしょう。
このように決算書は、企業外部の関係者に対して広く影響を及ぼすものですから、作成したあとの手続きについても、会社法が詳細に定めて規制しています。本稿では会社法の観点を中心に決算書を作成したあとの法的な効果について説明します。
7-1 決算書の位置づけ
企業は通常1年間を一つの期間として設定し、企業活動をお金の価値に換算したうえで計算して、書類にまとめます。これがいわゆる決算書です。
決算書は企業が作成するものですが、作成したあとは一体何に使うのでしょうか。これはまさに決算書を作成する目的ということになります。
まずはこの点について、会社法での決算書の位置づけから考えてみましょう。
一般的に「決算書」と呼ばれている書類ですが、会社法での用語は「計算書類等」となっています。具体的な書類の名称を挙げると、有名なものとして「貸借対照表」と「損益計算書」があります。このほかに「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」「事業報告」「附属明細書」が含まれます。
また、別の言葉で「財務諸表」や「財務書類」という呼称も一般的です。いずれも厳密に言えばそれぞれ定義がありますが、基本的には同じものを指していると考えて良いでしょう。そこで、本稿では「決算書」に統一して説明します。
さて、その決算書に関して最も重要なことは、全ての会社において作成が義務付けられている、という事実です。なぜなら、会社の活動は株主や債権者など、外部の関係者の権利や義務に影響を及ぼすため、決算書を作成することによって活動内容を明らかにする必要があるからです。
これが決算書を作成する目的です。
ただし、「決算書」と一口に言っても、前述のとおりその種類には様々なものがあります。実は、会社によって作成が必要な書類が異なってきます。それは会社の規模、株式の公開・非公開、組織の構造によって区別されます。
なぜなら、これらの要素というのは、その会社の活動が世の中に対してどれだけ大きな影響を及ぼすのかに深く関わってくるからです。規模が大きければ大きいほど、また株式を市場に公開しているような場合には、関係者の人数も多くなり、金額も高額になります。
世の中への影響が大きいほど、より透明性の高い情報開示や丁寧な説明が求められる、ということです。冒頭に列挙した決算書のメニューの範囲内で、作成が求められる書類が増えていくということです。
そして、組織の構造という点に関しては、決算書を作成したあとの手続きにも大きく関わります。この点について次節で説明します。
7-2 株式会社の「機関」とは?
株式会社には「機関」という概念があります。会社全体を一つのロボットや機械に例えるとすれば、「機関」とはその主要な部品やパーツを意味しています。
会社はパーツを組み合わせることで組織を設計します。この際、組織の実態に沿うように、会社法の認める範囲内である程度自由にパーツを組み合わせることができるようになっています。そこで具体的なパーツについて、代表的なものをいくつか挙げておきます。
まず、絶対に必要な機関は株主総会です。これは会社の最高意思決定機関であり、ロボットや機械に例えるとCPUやマザーボードに当たるでしょう。つまり命令を司る頭脳ですから、これが無ければ会社組織は動きません。
次に重要な機関は、株主総会の命令を具体的に実行するための装置です。この機関は取締役と呼ばれます。複数集まって取締役会を組織することもできます。また、会社外部に対する「顔」としての代表取締役を設置することもできます。
そして、取締役が株主総会の命令にちゃんと従っているかどうかを制御・チェックする装置が必要です。これが監査役です。複数集まって監査役会を組織することもあります。また条件に応じて監査委員会を組織することもできます。
基本的かつ主な柱となる機関はこの3つです。ちょうど国家における三権分立のように、それぞれが監視や牽制をしながら組織のパフォーマンスを最大化するように工夫されています。
ただし、前述のとおり会社の規模や実態に応じて、これよりも若干シンプルな機関設計にしたり、重厚な設計にしたりという幅がある程度認められています。
8 株主総会と決算書の関係とは?
前節では、株式会社の機関について概観しました。続いて、決算書に対してのそれぞれの機関の関わりについて整理します。
ここでは、決算書を作成した後はどうなるのか、という観点から会社の機関について確認をしていきます。
8-1 決算書の承認とは?
会社法において、決算書の作成が義務付けられていることは既に説明しましたが、さらにもう一つ、重要な規定があります。それは、決算書を株主総会などにおいて承認を得ることについても、義務付けられているということです。
理由は2つあります。まず1つは、決算書が剰余金分配、つまり配当の前提となるからです。配当の額がいくらになるのかは、株主にとって重大な関心事です。また、配当は会社財産が社外に流出することを意味しますから、株主だけでなく、債権者に対しても大きな影響を与えます。
このため、会社法では、配当可能額の算出方法を定めることによって株主および債権者間の利害関係を調整しています。そして、配当額の計算は決算書にもとづいて行われるため、計算のベースとして正しいものであるという前提が必要となります。そこで、株主総会などで承認を受ける必要があるということです。
もう1つは、決算書を株主総会の承認事項とすることによって、会社の経営について株主が監督する機会となるからです。株式会社の制度上、所有と経営は分離しているので、株主はふだんの経営活動については経営者に任せています。しかし、株主はその経営者を監督する立場にあるため、最終的には何らかのジャッジを行うことになります。
そのジャッジは、経営者の再任あるいは解任であったり、重要な投資案件についての経営判断であったりします。このようなことを判断するために、経営者から提出された成績表のように、決算書を確認して、問題が無ければ承認します。
8-2 報告のみで良い場合とは?
ここまで、株主総会において決算書の承認が必要という前提で話をすすめてきました。しかしながら、これには例外があります。ここで関係してくるのが、前述した会社の機関設計です。
決算書について、承認が必要となる理由については既に述べたとおりです。しかし、世の中には一口に株式会社と言っても、株主一人で経営者を兼務しているような一人会社から、社員数万人の上場企業まで様々な会社があります。
決算書の承認が必要な趣旨はわかりますが、例えば上場企業のような大規模な会社では株主の数も多く、その中で経営に積極的に関わろうとする、あるいはその能力を持っているような株主はほとんどいません。
このような場合は、一定の条件をクリアする必要があるものの、取締役会の承認によって決算書を確定させることができます。そのため株主総会には報告のみで良いこととされています。前述した株主によるチェックの機能を一部放棄することで、株主総会や会社経営を円滑にしようとすることがその趣旨です。
さてその条件とは、決算書について会計監査人の監査を受け、適正とされていること、またその手続について監査役等の反対意見も出ていないことです。これによって、外部の会計専門家によって決算書がある程度正確であることが保証されています。そして、会社にとっても株主にとっても特段問題が無いことが担保されていると考えられるのです。
このような条件をクリアするには、取締役会、監査役(会)、会計監査人の各機関が設置されていることが必要になります。会計監査人には公認会計士あるいは監査法人しかなることができません。ですから現実には、相当大規模あるいは上場企業を想定した条件であると考えて良いでしょう。
9 決算書の効力とは?
前節で確認したように、決算書の承認は法的に必要な行為ということになります。ですから、株主総会の承認は決算書が有効であるために必要な要件であることになります。
9-1 決算書の有効性
あるいは、前節で確認したように、取締役会による承認で代替する場合もありますが、これは株主総会の手続きを簡略化しているに過ぎないので、いずれにしても承認が必要であることに変わりありません。
それでは、仮に承認を得られなかった決算書はどうなるのでしょうか。
いくつかの状況を仮定する必要があります。例えば決算の内容に不備がある、あるいは会計上の判断について株主の意向に沿わなかったとして不承認になった場合は、決算書の作り直しになるでしょう。決算書を修正し、それが改めて承認されれば特に何の問題もありません。承認が得られるまで作り続けます。
このような事例では未承認の決算書が世の中に出ていくことはありません。ですから、現実的に頻繁に発生する事例でもありませんし、発生したとしてもその事実が株主以外の関係者の目に触れることは、おそらくほとんど無いでしょう。
しかし、場合によって、事後的に効果が取り消される場合があり、この場合は非常に影響が大きいため注意が必要です。
9-2 決算書の承認取り消しを求めた裁判
事後に、決算書の有効性が議論になった事件として、有名な判例があります。
本件では、会社は有効な手続きを経ないで株主総会を強引に終決させ、その議決にもとづいて配当を実行しました。
この点について株主Xは、株主総会の手続きにかかる瑕疵を理由として、決議の取り消しを求めました。
本件で争点となったのは、株主総会決議そのものの有効性であり、決算書に特化したものではありませんでした。しかしながら、株主総会そのものの有効性が否定されれば決算書の承認という行為も取り消されます。
また、事件が発生してから、判決まで10年以上を要しました。当時の決算書の効力が否定されれば、それ以後の決算書への連続性にも影響を及ぼすことから注目を集めました。
結論として裁判では、有効な手続きを経ていないことが確認され、株主総会決議は取消しとなり、決算書は無効であることが確定しました。そして、注目されていた、それ以降に承認されてきたはずの各年度の決算書も「不確定なものになると解さざるを得ない」という見解が示されたのです。(最判昭和58年6月7日)
この結果からまた、当該決算書にもとづく配当についても、根拠がありませんから遡って効力を失うことになります。会社は既に交付した配当について、返還を求めることができることになりました。
このような事件は珍しいケースではありますが、株主総会決議の取消訴訟が起こると、以後の様々な影響が懸念されます。特に、決算書の承認取消しは、それ以降の決算が全て適正であったとしても、遡って修正が必要になってしまいます。
決算書の承認というのはそれだけ慎重を要する手続きであることに留意すべきでしょう。このようにして会社法は株主の権利保護を実現しようとしているのです。
10 まとめ
決算の早期化と決算後にできる節税対策をさまざまな角度から考えてみました。
投資家・株主、経営者、従業員にとって、大きな意味を持つ取組であることがわかりました。
その中でも特に会社の経営を任されている経営者にとっては、決算の早期化の持つ意味は特別です。
一つは経営活動のスピードアップです。月次決算を早期化してゆくことで、会社全体の現状把握と、今後の対策を速やかに打ち出すことができます。
もう一つは業務改善です。月次決算を早期化するということを切り口に社内の業務改善を進めてゆくことができます。無駄な作業や手続きを減らし、スピード感のある業務体制を作り上げます。
会社の経営資源は限られています。特に中小企業では人材や設備・システムなど大手企業にはどうしても太刀打ちできない点もあります。
しかしスピード感や小回りが利きやすい点は中小企業ならではの強みです。社内の仕組みを整え、コミュニケーションをとりながら業務改善を行ってゆけば、限られた経営資源をより有効に活用することができます。
決算の早期化への取り組みの中で、そうした強みを磨き上げてゆきましょう。