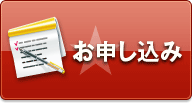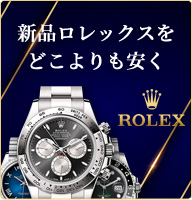会社が行う事業の内容を「目的」と言い、会社は「目的」の範囲内で権利を有し義務を負う「法人格」を取得します。
しかし、会社を設立すれば、どんな事業も自由に行えるようになる訳ではありません。
会社が行える事業は、会社の根本規則を定めた「定款」に記載された事業の範囲に限定されます。
会社の設立の際の目的は、細かく具体的に定めることは逆効果ですが、第三者に理解できる程度の目的を定めることは重要です。
書籍やインターネット、また、会社設立の専門家と相談して決定して下さい。後で不備があった場合は、定款を変更する必要があり、これには、登記変更手続きに伴う費用が発生します。
目次
- 「目的」決定の3要素
- 目的決定の際の注意点
- 目的を節操無く記載することは避ける
- 同業他社の「登記事項証明書」の閲覧
- 法務局で「目的」についてアドバイスを求める
- 目的の最後には、「付随または関連する一切の業務」と記載する
- 目的の書き方
「目的」決定の3要素
会社は、定款に記載された目的の範囲内で権利・義務の主体となり、目的として記載されていない事業は法律上行えません。
また、目的には前提として、①「適法性」、②「明確性」、3「営利性」、の3つの要素が必要です。
①「適法性
「適法性」とは、会社は公序良俗の反する事業を目的とすることはできないと言うことです。例えば、「麻薬販売・輸入」や「詐欺強迫による恨み倍返し」は、当然ながら目的とすることはできません。
②「営利性
 「営利性」とは、文字通り会社は営利を目的とする団体組織でなければならないと言うことです。
「営利性」とは、文字通り会社は営利を目的とする団体組織でなければならないと言うことです。
会社の実質的オーナーは、株主等の資金を払い込んだ者であり、会社は事業を行い、これらのものに対して利潤を分配する組織です。
ボランティアや寄付活動といった事業では営利性は追求されず、会社本来の趣旨に反してしまいます。
ただ、会社が行う社会貢献は、会社の付随的事業として行う分には、当然ながら否定されません。会社も社会を構成する一員なので、良き市民として社会還元することは、むしろ当然とも言えます。
③「明確性」
「明確性」は、会社が定めた目的は、一般人が分かるような言葉で表現される必要があると言うことです。
例えば、新しい技術が開発され、業界では、一躍話題の中心となっているような言葉でも、一般に広く周知されていない言葉は、「明確性」に欠けると言わざるを得ません。先述しましたが、会社は社会の一員として事業を行うので、一般人が理解できる明確な言葉を事業の目的として挙げる必要があります。
目的決定の際の注意点
①
会社が目的を定める場合にまず考慮すべきは、具体的に決定している会社設立後すぐに開始する事業目的の他に、将来行うかもしれない目的や興味場あり、行ってみたい事業目的も、定款の目的条項に記載しておくことが重要です。
後になって、目的を変更したり追加する場合は、定款変更する必要があり、定款変更には登録免許税が発生します。
会社の目的は、定款に記載すれば必ず事業として行わなければならないと言う訳ではないので、会社の設立時には、事業の発展や自分の気持ちをよく考えて、ある程度幅広い目的設定を行ってください。
この点でも、会社設立業務に精通している専門家の意見は、自分の考えの枠を超える提言ができるので非常に役に立ちます。
②
次に、目的については、ある程度抽象的な表現でも登記は可能と思われますが、抽象的な目的を登記した場合は、行政機関の業法上の許認可が必要な事業の場合には、許認可要件がクリアできない場合があるので注意が必要です。
例えば、「派遣業」とした会社の目的では許可されません。この場合は、「一般労働者派遣業」や「特定労働者派遣業」といった法律上の要件をクリアした具体的な目的にする必要があります。
また、業種によっては、兼業禁止業種も存在します。兼業禁止業務を会社の目的に併記して掲載すると兼業禁止放棄に抵触し、会社設立そのものがとん挫する場合も考えられます。
そこで、少しでも疑問がある場合は、許認可の専門家である行政書士や監督官庁の担当者に相談することをお薦めします。
目的を節操無く記載することは避ける
会社の目的に記載する事項に制限はないので、公序良俗に反する目的でない限り、極論すればいくらでも記載しても構いません。
ただ、節操無く目的の数を羅列して記載すると、会社の取引先は、会社に対して疑念を生むことが考えられます。
「この会社は一体何を事業の柱とするのか」と言う疑念を持たれる場合もあります。
社会的に知名度のある会社で重要な取引業務を行っていた方が会社設立する場合でも、個人的に起業する際は、あくまでも新規事業なので、取引先は、あなたの会社に対して「与信審査」を行います。
登記事項証明書を確認して取引しても問題がないかを検討します。
この時、あまりに多くの目的を記載している場合は、信用を失う事に繋がる場合があるので注意が必要です。将来やりたいことが多い場合もあるでしょうが、まずは、目的の数を最大でも10個程度におさめておくことをお薦めします。
また、借入の際に、ある特定の業種には融資が下りない場合もあるので、日本政策金融金庫や地方自治体の融資制度を活用しようとお考えの方は、これらの機関へ目的を提示して判断を仰いでください。このような場合も、会社設立の援助業務に豊富な経験を持つ、税理士や司法書士、行政書士等の専門家と相談すれば、問題点と指摘してもらうころができ、無駄な労力と費用を軽減することができます。
同業他社の「登記事項証明書」の閲覧
目的を定めるには、まず、会社の設立後取り組む事業内容と近い将来行いたい目的を書き出してみるとよいでしょう。
会社の事業目的は、各会社のホームページにも掲載されている場合もあります。
また、同業他社の「登記事項証明書」を見ることも可能です。
法務局に赴き、どんな会社がどのような目的と定款に記載しているのかを「登記事項証明書」を入手して確認することも、経験や活きた知識の習得として重要なことなのです。
また、インターネット上や起業を応援する書籍には、業種ごとの目的が具体的に記載されているので、これらの情報から目的を取捨選択することもよいでしょう。
詳しい注意点は、専門家の知恵と経験を活用することになりますが、会社の目的を考えるには、人任せではなく、自分で納得のいくまで考えた目的にすることが重要です。
法務局で「目的」についてアドバイスを求める
 会社設立は、初めて設立する者にとっては複雑な手続きを伴い、心配と苦労が生じる業務と言えます。
会社設立は、初めて設立する者にとっては複雑な手続きを伴い、心配と苦労が生じる業務と言えます。
せっかく会社設立の登記までこぎつけたにも関わらず、「目的」が認められず、登記承認が得られない場合もあるのです。
この点、法務局には、この「目的」で登記ができるか否かの相談ができる「登記申請窓口」が設けられ、専門官がこの相談業務にあたっています。
会社設立の必須書類である「定款」の作成作業が概ね完了した場合は、法務局で「目的」等の記載事項を確認してもらいましょう。
またこの時、登記申請jに必要になる「印鑑届出書」、「印鑑カード交付証明書」、「OCR用紙」も入手しておきましょう。
目的の最後には、「付随または関連する一切の業務」と記載する
定款の目的を変更したり追加するのは、定款変更手続きやこれに伴う登録免許税が必要になりますが、新たに開始する事業目的でも、目的条項の最後に、「前各号に付随または関連する一切の業務」と記載していれば、これに含まれる目的は新たな登記変更が必要ありません。
この文言は非常に有効なので、是非目的条項の記載の最後に加えてください。
目的の書き方
ここでは、簡単な目的の書き方のひな型を参考までに記載しておきます。
第○条 当会社は、以下の事業を営むことを目的とする。
1・家庭用電化製品の輸入・販売
2・家庭用並びに業務用生活雑貨、食器等の輸入・販売
3・インターネットやカタログによる通信販売
4・家庭用の浄水器レンタル・販売
5・住宅のリフォーム、増改築、インテリアコーディネート業務
6・以上前各号に付随または関連する一切の業務
様々な媒体で、会社の目的についての参考資料が提示されているので、これらを活用し、これからの事業目的について決定して下さい。
また、目的の概要が固まったら、行政書士・司法書士、または、税理士等で会社設立業務に精通している専門家のアドバイスを受けてください。