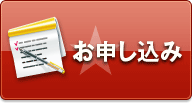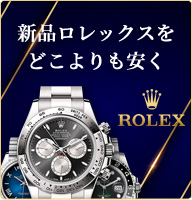2015年、多様で柔軟な働き方の実現を目的に、労働者派遣法が大きく改正。従来、企業にとって最大3年だった派遣社員の受け入れ期間を延長するなどの措置がとられました。
従業員を派遣として雇う場合、多くの労働関係の法律が関係します。
会社経営者に求められる労働者派遣法改正のポイントをまとめました。
世界最大と言われる中国の携帯電話市場でいま何が起きているのでしょうか。
目次
- 1 労働者派遣法とは
- 2 改正労働者派遣法のポイント
- 2-1 派遣期間の見直し
- 2-2 派遣労働者の雇用の安定措置
- 2-3 均衡待遇の推進
1 労働者派遣法とは
労働者派遣法は、派遣事業を適正に運営することを目的に派遣労働者の権利を守り、雇用の安定を図るために制定された法律です。日雇い派遣の原則禁止など、時代ごとの働き方に合わせて改正が重ねられてきました。
そもそも派遣とは、派遣元となる人材派遣会社に登録している者を、派遣先の企業へ派遣して、派遣先企業の担当者のもとで労働する雇用形態になります。
正社員やパートタイマーが企業と直接雇用契約を交わしているのと異なり、派遣者が雇用契約を結ぶ相手は派遣先の会社ではなく、派遣会社になります。
派遣会社は、厚生労働省の許可を得て派遣事業を営み、派遣社員に仕事先を斡旋するのが主な業務です。
2 改正労働者派遣法のポイント

会社経営者が知っておきたい改正点は、①派遣期間の見直し、②派遣労働者の雇用の安定措置、③均衡待遇の推進の3つになります。
2-1 派遣期間の見直し
企業が派遣労働者を受け入れることができる期間(派遣可能期間)は、原則3年が限度です。3年を超えて派遣労働者を受け入れようとする場合は、過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。
つまり、企業は労働組合と相談して3年ごとに派遣労働者を入れ替えることで、派遣労働者を受け入れ続けることができます。
派遣労働者の視点からみれば、派遣先の企業で配属される部署を3年ごとに異動することで、その会社で働き続けることができます。
ただし、派遣会社に無期雇用されている派遣労働者を受け入れる場合や、60歳以上の派遣労働者を受け入れる場合、期間制限はありません。
2-2 派遣労働者の雇用の安定措置
派遣労働の雇用が安定を図るため、派遣会社は、継続して就業を希望する有期雇用派遣労働者について、以下のいずれかの措置を実施しなければなりません。
| 1 | 派遣先企業への直接雇用の依頼 |
|---|---|
| 2 | 新たな派遣先の紹介 |
| 3 | 派遣元での無期雇用 |
| 4 | その他安定した雇用の継続を計るために必要な措置(次の派遣先が見つかるまでの有給の教育訓練、紹介予定派遣など) |
企業は、派遣会社が派遣労働者の雇用の打診をしてきたときに備えて、採用するか否かの準備をしておきましょう。
2-3 均衡待遇の推進

派遣労働者と、派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るため、派遣を受け入れる企業に、次のような義務が課されています。
| 賃金水準の情報提供の配慮義務 | 企業は、派遣会社が派遣労働者の賃金を適切に決定できるよう、必要な情報を提供する |
|---|---|
| 教育訓練の実施に関する配慮義務 | 企業は、派遣労働者に対し業務と密接に関連した教育訓練を実施する場合、派遣会社から要請があったときは、派遣労働者に対してもこれを実施する |
| 福利厚生施設の利用に関する配慮義務 | 企業は、派遣先の労働者が利用する福利厚生施設(食堂、給湯室、休憩室、更衣室など)については、派遣労働者に対しても利用させる |
| 派遣料金の額の決定に関する努力義務 | 企業は、派遣労働者の賃金について、企業で同種の業務に従事する労働者の賃金水準と均衡の図られたものにする |
| 企業は、労働者派遣契約を更新する際の派遣料金の額の決定に当たっては、就業の実態や労働市場の状況等に加え、業務内容等や要求する技術水準の変化を勘案して決定する |
この度の改正派遣法では、企業が直接雇用の依頼に応じる義務は盛り込まれておらず、派遣労働者の雇用の安定の実効性を疑う声も少なくありません。
派遣先の会社が派遣労働者を雇うさいには、将来正社員としての雇い入れを考慮するなど、安定した雇用の機会が提供できるといいでしょう。