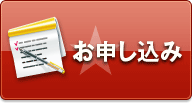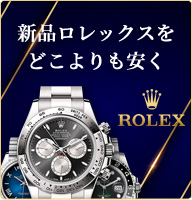中小企業の意味を定義するのは1963年に制定された中小企業基本法です。この法律は、所得倍増計画を策定した当時の池田勇人首相の主導のもと、①中小企業の国民経済における役割の強調、②経営の近代化、③生産性の格差の是正を目的に制定されました。
中小企業基本法は中小企業の定義を業種別によって変えています。また、法人税法でもその定義は異なります。詳しく見ていきましょう。
目次
1 中小企業の定義
基本法によれば、中小企業は次のように定義されます。
1-1 中小企業基本法による定義
| 業種 | 定義 |
|---|---|
| 卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
| 小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
| サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
| 製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社または常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
(参照:中小企業庁)
中小企業の定義の条件がもっとも広いのが製造業・その他で、狭いのが小売業となります。資本金3億円、従業員300人と聞くとはたから見れば大企業のように見えますが、かりに年商が1000億あったとしても資本金を増やさない限り、中小企業に分類されたままです。
また中小企業信用保険法などの中小企業関連立法では、政令により次の業種のものを中小企業として定義します。
| 業種 | 定義 |
|---|---|
| ゴム製品製造業 | 資本金3億円以下または従業員900人以下 |
| 旅館業 | 資本金5千万円以下または従業員200人以下 |
| ソフトウエア業 情報処理サービス業 | 資本金3億円以下または従業員300人以下 |
1-2 法人税法による定義
法人税法によれば、中小企業は業種を問わず、資本金が1億円以下の会社はすべて中小企業に分類されます。
| 業種 | 定義 |
|---|---|
| 卸売業 | 資本金1億円以下 |
| 小売業 | |
| サービス業 | |
| 製造業その他 |
1-3 みなし大企業制度
中小企業基本法においても法人税法においても、親会社から相当の出資をうけている企業はすべてみなし大企業とされ、中小企業が受ける助成金の対象外となる場合があります。
・みなし大企業の条件
- 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
- 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
(参照:平成26年度 消費者志向型地域産業資源活用新商品開発等支援事業 公募要項における「みなし大企業」の定義)
2015年、経営再建中のシャープが資本金を1億円に減らして法律上の中小企業になろうとしたことに対して批判が集まり、のちに撤回するという騒ぎになりました。中小企業になれば税制上の優遇措置を受けることができますが、企業再生のためとはいえ、売上高2兆円の大企業の“奇策”に対して当時の宮沢洋一経済産業相も記者会見で「若干、企業再生としては違和感がある」と発言。
各方面から批判を受けたシャープは、資本金を5億円に減らすことに変更することで落ち着きました。

(参照:産経ニュース)
2 最近の改正の内容
中小企業基本法は1999年と2013年に大きく改正されました。詳しく見ていきましょう。
2-1 1999年の改正
オイルショックやバブル経済の崩壊をうけて抜本的に改正され、基本方針は①経営の革新及び創出の促進、②中小企業の経営基盤の強化、③経済的社会的環境の変化への適応の円滑化となりました。
さらに中小企業支援法、新事業活動促進法、ものづくり高度化法、地域資源活用促進法、経営承継円滑化法、中小企業金融円滑化法などの関連法が制定されました。
2-2 2013年の改正
少子高齢化や人口減少、都市一極集中、国際競争の激化などを受けて、小規模事業者を中心とした中小企業施策の再構築が行われ、小規模企業活性化法が制定されました。
さらに2014年には、小規模企業を中心に据えた新たな施策体系を構築するとの理念のもと、小規模企業振興基本法が制定されました。(参照:経済産業省「中小企業関連法制の変遷」)