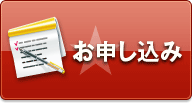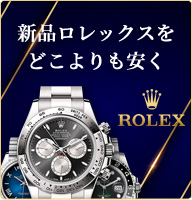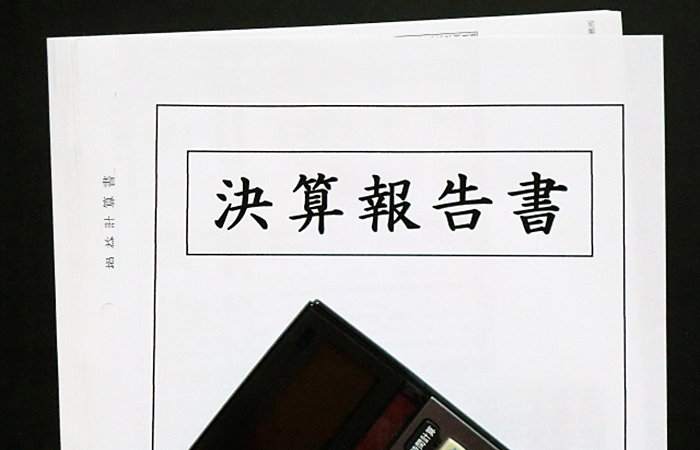
決算書をわざわざ他者に公開する必要はないだろう!と考えている方もおられるでしょうが、株式会社等には決算公告という法的な開示義務が課せられています。違反の場合には取締役等に罰則が適用されますが、現実的な適用がないことから大半の会社等は決算公告を行っていません。
ここでは決算公告の全貌を明らかにして、法的公告である決算公告の意義やメリット・デメリットを取り上げるとともに、それらを踏まえた活用の仕方を紹介しましょう。
1 決算書の開示と決算公告
企業の経営状態を知るにはその決算書類等を確認するのが最も手っ取り早い方法といえるでしょう。ここでは決算書類等の開示や公告が法的にどう扱われるかを説明します。
1-1 決算書の開示の必要性とその法的な位置づけ
自分が勤める会社の決算書類が公開されていな場合に、経営者や上司に見せてもらえるように頼んだが断られた、という方もいるのではないでしょうか。こうした経験のある方の中には「本当に見せられないのか?」と疑問を抱くかもしれませんが、その対応は誤っているとは言えないのです。
会社法442条で決算書の備え置きと閲覧に関して次のような内容が定められています。
・株式会社は、各事業年度に係る計算書類および事業報告並びにこれらの附属明細書や臨時計算書類を定められた期間にその本店に備え置かねばならない。
・株主および債権者は、株式会社の営業時間内は上記の計算書類等(詳細は下記のとおり)を請求できる。
つまり、株主や債権者であれば、対象の株式会社に請求すれば決算書を開示してもらえる権利があるということです。他方、それらに該当しないその会社の社員や他の企業などはこの法律において開示してもらえる権利がないのです。
なお、株主や債権者が対象の株式会社に決算書類の開示を請求する場合の取り決めとしては以下の内容が定められています。
・会社法442条3項
会社の営業時間内は、下記の決算書類等をいつでも請求できる。
・3項の1号
計算書類等が書面で作成されている場合は、書面または書面の写しの閲覧を請求できる。
・3項の2号
前号の書面の謄本または抄本の交付を請求できる。
・3項の3号
計算書類等が電磁的記録で作成されている場合は、電磁的記録に記録された事項を表示したものの閲覧を請求できる。
・3項の4号
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法で株式会社の定めたものにより提供することを請求できる。またはその事項を記載した書面の交付を請求できる。
なお、会社の取締役などが株主や債権者からの開示請求を断った場合は、罰則が課せられます。会社法976条では会社の取締役等が以下のケースに該当する場合、「百万円以下の過料に処する」と規定されているのです。
・会社法976条4項
「正当な理由なしに書類や電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧、謄写または書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること、或いはその事項を記載した書面の交付を拒んだ場合」
もちろん書類や電磁的記録を備えなかった場合も上記の罰則に該当しますので、経営者の方は確実に備えておかねばなりません。
1-2 決算公告とは
上記1-1では決算書類の開示義務については説明しましたが、それとは別に株式会社には貸借対照表等の公告の義務があります。ここでは決算公告の法的な取り扱いを含めその全体的な内容を説明しましょう。
・公告とは
「公告」とは、国や公的機関などが広く一般公衆にある事項を知らせることで、官報・日刊新聞等へ文章でもって掲載・掲示することを指します。
法律によって定められた公告は「法的公告」と呼ばれています。会社法に関連した法的公告の対象は「合併」、「会社分割」、「準備金減少」、「組織変更」、「解散」のほか「決算」などです。これらの法的公告は株式会社等がその組織の重要事項をステークホルダーに広く知らせるための規定であり、その中に「決算公告」が含まれています。
・決算公告
会社法第440条(計算書類の公告)では、株式会社は定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社*の場合は、貸借対照表および損益計算書)を公告しなければならない、と定められています。
(*大会社とは、最終事業年度の貸借対照表における資本金の額が5億円以上であるか、もしくはその貸借対照表における負債の部の合計額が200億円以上である会社のこと)
つまり、株式会社は決算に関する公告の義務があるわけです。また、この義務を怠った場合、会社法第976条第2項での罰則規定が適用されます。なお、罰則については旧商法時代にも規定されていました。
しかし、このように罰則規定はあるものの実際にこの公告義務を履行している会社はほんの一部に限られており、規模の大きな会社でも長年に渡って実施していないケースもみられます。また、現実的には不履行であっても罰則を受けているケースが見当たりません。公告には一定の費用と労力がかかりますが、罰則も現実的には課せられないということもあり公告しない会社が圧倒的に多い状況であるといえるでしょう。
1-3 決算公告の今後の動向
新会社法が施行(平成18年5月1日)されたことにより決算公告の取り扱いに変化が生じる可能性が出てきました。
新会社法により株式会社の最低資本金規制がなくなって、資本金1円からの会社設立も可能です。加えて会社の機関においても取締役が1名でも済ませられるようになっています。旧商法時代には特例制度もありましたが、株式会社の最低資本金は1,000万円で、会社の機関も取締役3人、監査役1人の選任が必要でした。つまり、会社法により株式会社の設立がお手軽になったわけです。
新会社法は起業家にとっては設立のハードルが下がるありがたい制度といえるでしょう。しかし、取引先や資金提供者にとっては経営基盤が脆弱な株式会社が増えることになるので、関わることでのリスクが高まったともいえます。そのため株式会社を取り巻くステークホルダーから決算公告に対する要請が強まる可能性が生まれてきたわけです。今後は公告義務違反に対する行政の考えも変わり、罰則の適用へと動くかもしれません。
ステークホルダーからの要請や行政の動きなどに注視しつつ、株式会社等は決算公告によるメリットなども考えて、その前向きな対応が求められそうです。
1-4 決算公告の対象の例外
株式会社は原則的に決算公告を実施する義務がありますが、金融商品取引法24条1項で規定されている有価証券報告書の提出義務を有する会社は対象外になります。
これに該当する会社は、「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」(EDINET)で決算内容が公開されているため公告の必要がないのです。また、通常これらの会社では自社のホームページのIRコーナーで決算書類等を通常公開しているため、EDINETで確認する必要もないでしょう。
また、特例有限会社も決算公告する義務を負いません。会社法が施行される前の有限会社には株式会社と異なり決算公告の義務はなかったですが、会社法施行後の特例有限会社も同様の扱いになるわけです。特例有限会社は旧有限会社法での有限会社と同じ利点が得られますが、一定の手続を踏めば株式会社へ移行することも可能です。
1-5 決算公告の方法(官報、日刊新聞紙、電子公告)
会社法第939条では会社等はその公告方法として、官報、日刊新聞紙、電子公告のいずれを定款で定めることになっています。
・官報、日刊新聞紙
決算公告を行う場合、定款で公告方法として官報または日刊新聞紙とした会社は貸借対照表の「要旨」で公告することが可能です。官報や日刊新聞紙への決算公告には何万円・何十万といった費用がかかるため、要旨の公告にすることで費用負担の軽減が図られているとみられています。
・電子公告
電子公告で登録している会社は、定時株主総会の終結後速やかに貸借対照表の情報を、定時株主総会の終結の日後5年間継続してホームページ上に開示しなければなりません。なお、電子公告の場合は貸借対照表の要旨による公告は不可で、全文で公告する必要があるので注意しましょう。決算公告用のホームページについて、他の公告事項に関するホームページとはリンクのない別のアドレスの登記も可能です。
また、官報や日刊新聞紙で登録している会社でも電子公告による決算公告ができますが、貸借対照表等の全文での掲示となります。加えてこの場合には、貸借対照表等を掲示するホームページのURLを登記しなければなりません。(会社法第911条第3項第26号)
決算公告のみを電子公告で行う場合、URLの登記申請(変更登記申請)が必要となり申請1件につき登録免許税3万円が必要となります。官報や日刊新聞紙への掲載では毎年何万円・何十万円といった費用がかかるので、電子公告はコスト面では極めて経済的といえるでしょう。
1-6 決算公告の罰則
決算公告を怠ると会社法第976条第2項(過料に処すべき行為)の罰則規定が適用され「100万円以下の過料」に処されることとなります(実際に適用された例はないとみられています)。また、不正な公告を行った場合も同様です。この罰則の対象は会社自体ではなく取締役や執行役などの個人になります。
法定公告である決算公告で虚偽や不正な公告を行った場合、公告の効力が喪失することになりかねず、また刑事上や民事上の責任が問われるケースもあり得るでしょう。
2 決算公告の行い方
ここでは官報、日刊新聞紙と電子公告による具体的な決算公告の仕方を確認していきましょう。
2-1 官報での決算公告の掲載の仕方
ここでは国立印刷局の「法定公告について」に基づき官報での決算公告の掲載方法や費用などを紹介します。
決算公告は、会社法および会社計算規則にしたがって、大会社以外の会社(非公開会社と公開会社)および大会社(非公開会社と公開会社)ごとにその会社に応じた決算公告の記載の仕方が決められています。参考として、①「大会社以外の会社で非公開会社」と②「大会社で公開会社」の公告の仕方を説明しましょう。
なお、表示言語については日本語で表示することになっていますが、その他の言語で表示しても不当でなければ可能です。
要旨の金額の表示単位は百万円単位または十億円単位で表示できます(ただし、会社の財産または損益の状態を適切に評価できない可能性がある場合には、適当な単位で表示することもできます)。
内閣府が官報を行政機関の休日以外の毎日に発行し、国立印刷局で官報の編集、印刷およびインターネット配信が行われています。また、官報での公告の申込みや問合せは、指定の最寄りの取次所へ行うことになっています。
①大会社以外の会社で非公開会社の場合
貸借対照表の公告が必要ですが、損益計算書の公告は不要です。貸借対照表の要旨は、おおよそ以下のように記載されます。
貸借対照表
| 資産の部 | 流動資産 固定資産 繰延資産 |
|---|---|
| 負債の部 | 流動負債 引当金(設けた場合) 固定負債 引当金(設けた場合) |
| 純資産の部 | 株主資本*1 評価・換算差額等*2 新株予約権 |
*1 株主資本に関する項目は以下に示す項目で分類する必要があります。
- 資本金
- 新株式申込証拠金
- 資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金 - 利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金 - 自己株式
- 自己株式申込証拠金
*2 評価・換算差額等に関する項目は以下に示す項目で分類する必要があります。
- その他有価証券評価差額金
- 繰延ヘッジ損益
- 土地再評価差額金
なお、当期純損益金額を付記しておかねばなりません。
②大会社で公開会社
貸借対照表および損益計算書の公告が必要で、貸借対照表および損益計算書(大会社のみ)の要旨は、おおよそ以下のように記載されます。
貸借対照表
| 資産の部 | 流動資産 固定資産 有形固定資産 無形固定資産 投資その他の資産 繰延資産 |
|---|---|
| 負債の部 | 流動負債 引当金(設けた場合) 固定負債 引当金(設けた場合) |
| 純資産の部 | 株主資本*1 評価・換算差額等*2 新株予約権 |
*1 株主資本に関する項目は以下に示す項目で分類する必要があります。
- 資本金
- 新株式申込証拠金
- 資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金 - 利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金 - 自己株式
- 自己株式申込証拠金
*2 評価・換算差額等に関する項目は以下に示す項目で分類する必要があります。
- その他有価証券評価差額金
- 繰延ヘッジ損益
- 土地再評価差額金
- 損益計算書
- 売上高
- 売上原価
- 売上総利益または売上総損失
- 販売費および一般管理費
- 営業利益または営業損失
- 営業外収益
- 営業外費用
- 経常利益または経常損失
- 特別利益または特別損失
- 税引前当期純利益または税引前当期純損失
- 法人税、住民税および事業税
- 法人税等調整額
- 当期純利益または当期純損失
※その他、各項目については、株式会社の損益の状態を明確にしなければならない場合、重要な科目に適宜細分する必要があります。また、当該項目に関する利益または損失を示す適切な名称を付さなければなりません。
③官報での掲載費用
平成28年4月1日現在の掲載料金は以下の通りです。
・枠組公告料金
枠組公告は、1ページ(A4判)を24枠(4段×6枠)として行われます。 1枠のサイズは、横2.9cm×縦6.1 cmで、 料金は1枠につき36,489円(税込)です。
・大会社以外の会社の例
(1)2枠で72,978円(税込)
(2)3枠で109,467円(税込)など
・大会社以外の会社(公開会社)の例
(1)3枠で109,467円(税込)など
・大会社(公開会社)の例
(1)8枠で291,912円(税込)
(2)4枠で145,956円(税込)など
④公告の申込みから掲載までの手続等の流れ
(1)申込み・入稿[企業]
官報での公告に関する申込みや問合せは、最寄りの取次所へ連絡します。インターネット、FAX、郵送、来店などの方法で、申込書や原稿を送ることになります。
(2)連絡および原稿の作成[取次所]
掲載日や原稿の内容について取次所から連絡があります。その内容にしたがって取次所においてゲラが作成されます。
(3)ゲラ拝(校正)[企業]
作成されたゲラは依頼の会社等に渡され、その会社等は誤字脱字の有無などの確認をしなければなりません。ただし、掲載までの期間があまりない場合、ゲラ拝が省略されることもあるので注意が必要です。
(4)校了[企業]
ゲラ拝(校正)の結果、修正の必要がある場合は、その指示を出さなくてはなりません。修正が不要の場合はその旨の連絡をします。なお、校了の連絡をした後は、原則的に修正・取消しの対応はできなくなります。
(5)印刷および掲載
校了後、ゲラは国立印刷局に入稿され印刷および掲載されることになります。
2-2 日刊新聞紙での決算公告の掲載の仕方
定款に定めることにより決算公告を日刊新聞紙で行うことも可能です。一般的な日刊新聞紙で決算公告を行う場合、費用は官報よりも高額になりますが、官報以上に広く一般の人々の目にするところとなるでしょう。
①日刊新聞紙での決算公告の内容
決算公告の掲載内容は官報と同様です。大会社以外の会社(非公開会社と公開会社)および大会社(非公開会社と公開会社)の内容を簡単にまとめると下表のようになります。
| タイプ | 規模 | 株式の譲渡制限 | 決算公告の内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大会社 | 公開会社 | 貸借対照表(固定資産および負債細分)と損益計算書 |
| 2 | 大会社 | 非公開会社 | 貸借対照表と損益計算書 |
| 3 | その他の会社 | 公開会社 | 貸借対照表(固定資産および負債細分) |
| 4 | その他の会社 | 非公開会社 | 貸借対照表 |
②決算公告に使用できる日刊新聞紙
会社法第939条第1項で、会社の公告方法の1つとして、日刊新聞紙は「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法」と規定されています。
「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙」は法令等での明確な定義はないですが、政治、経済、社会、文化などに関する情報を広く一般の人に提供する日刊の新聞紙といえるでしょう。
例えば、日本経済新聞、産経新聞、讀賣新聞、朝日新聞、毎日新聞などの全国紙のほか、北海道新聞、東京新聞、中日新聞、西日本新聞、などのブロック紙も該当します。また、神戸新聞、京都新聞、河北新報、中国新聞、静岡新聞などの県紙も含まれます。
ただし、日刊新聞でもスポーツ、学術や特定の業界を対象とした新聞紙は広く一般の人を対象としていないため、決算公告に使用できる日刊新聞紙とはみなされないので注意が必要です。該当するかどうか判断できにくい場合はその新聞社や法務省法務局などに問い合わせるとよいでしょう。
③日刊新聞紙での決算公告の費用
日刊新聞紙での決算公告の費用は各新聞社によりさまざまですが、一般的に全国版の日刊新聞紙の広告料は高めといえそうです。例えば、日本経済新聞社の全国版の場合、その決算公告の広告掲載料は次のようになっています。
2段×7.8cm(縦約6.4 cm×左右7.8cm)の例:967,200円
4段×10.4cm (縦約12.8 cm×左右10.4cm)の例:2,579,200円
*新聞紙は一般的に縦に15段構成となっている
*広告原稿制作費と消費税は上記料金に含まれない
また、他の全国版の日刊新聞紙では以下のような価格帯がみられます。
A社→2段×5cm:170万円台
B社→2段×5cm:170万円台
C社→2段×5cm:50万円台
*社会面での掲載
県紙やその他の日刊新聞紙の広告掲載料は全国版に比べて割安に設定されるケースがみられます。
・中部地区の県紙の例:
2段×5cmの例:230,000円
・日刊工業新聞社の場合
2段(6.4cm)× 5 cmの例:90,300円
2段(6.4cm)× 10 cmの例:180,600円
日刊新聞紙への申込みや広告データの入稿方法などは各新聞社で異なるので事前に確認するようにしましょう。
2-3 電子公告での決算公告の掲載の仕方
平成17年2月1日に施行された「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律」により、それまで官報や日刊新聞紙に限られていた公告に電子公告が導入されました。つまり、この法律により会社等がインターネット経由で法定公告ができるようになったのです。
①電子公告とは
電子公告とは、官報や日刊新聞紙への掲載により実施していた合併、資本減少等の公告をインターネット上のホームページに掲載することによって実施することを言います(会社法第2条第34号等)。
この方法により、対象とする会社等のステークホルダーはインターネット経由でその会社等のホームページにアクセスすることで簡単にその公告内容を把握できます。また、掲載する会社等にとっては官報や日刊新聞紙よりも公告に必要な費用が少なくなるというメリットが得られるのです。
②電子公告の手続の流れ
法務省のウェブサイトにある「電子公告制度」のページには、下図のようにその手続の流れがフローチャートで示されています。なお、決算公告を電子公告で行う場合、下図の「登記申請を行う」までが主な対象となります。それ以降の手続は主に合併等の公告に関する内容となるので注意してください。
①定款に電子公告を公告方法と定める。既存会社の場合は定款変更する
↓
②登記申請を行う
↓
③電子公告調査機関に調査を委託する
↓
④電子公告調査機関は法務大臣に調査委託があったことを報告する
↓
⑤公告開始(電子公告調査開始)
↓
⑥公告期間終了(電子公告調査終了)
↓
⑦電子公告調査機関から会社に対し調査の結果が通知される
↓
⑧調査結果通知を「公告をしたことを証する書面」として合併等の登記申請書に添付
・定款の変更等
会社等が法定公告を電子公告で行うためには、定款にその旨を定めなければなりません。会社等を設立する場合、公証人の承認を受ける原始定款に「当会社(当法人)の公告は電子公告の方法により行う」旨を定めます。また、既存の会社等の場合は、同じ旨の内容に定款を変更する必要があります。この場合、ウェブページのURLまで定款に定めなくてもかまいません(会社法第939条第3項、一般法人法第331条第2項)。
なお、電子公告を公告方法とした場合、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない時は官報または日刊新聞紙のいずれかを定款に定められます。電子公告を公告方法とする場合は継続による公告が求められるので、サーバーの故障等で電子公告ができなくなる状態に備えて、代わりの公告方法も定めておくべきです。なお、この場合の代わりの公告方法に関しても登記しておかねばなりません。(会社法911条3項第29号)
・登記申請
会社等が定款の変更により電子公告を公告方法とする場合は、2週間以内に本店(主たる事務所)所在地の管轄登記所への登記申請が必要です。この場合、公告方法だけでなく公告ホームページのURL(注)に関しても登記しなければなりません。(会社法第911条第3項第28号イ、一般法人法第301条第2項第15号イ)
登記事項である公告ホームページのURL(登記アドレス)は、公告ページのURL(公告アドレス)、もしくは公告ページが複数となる場合に作成する共通ページのURLのどちらでも問題ありません。
なお、登記アドレスについては、一般的に変更の少ない自社ホームページのトップページ(例、http://www.○○○.co.jp/)のURLが採用されるケースが多くなっています。ほかにも電子公告のページや、電子公告ファイルなどを保管してもらっている外部のサーバー運営会社が指定するアドレスなども可能です。
外部のサーバー運営会社が指定するアドレスを登記アドレスにしておくと、自社のホームページをリニューアルしても変更登記しなくて済むというメリットが得られます。
・アドレスの例
登記アドレスの例としては、以下のようになります。
トップページの例:http://www.○○○.co.jp/
電子公告ページの例:http://www.○○○.co.jp/ir/houteikoukoku/
公告アドレスに関しては、公告が同時に複数開示されることもあるため日付や広告内容が判断できるようにするとよいでしょう。
公告アドレスの例:
http://www.○○○.co.jp/houteikoukoku/20170401kessan.pdf
*参考:電子公告調査機関への調査委託(決算公告は除く)
法定公告を電子公告で行う会社等は、公告期間中に電子公告が適法に実施されたか否かについて、法務大臣の登録を受けた電子公告調査機関の調査を受ける必要があります。(会社法第941条、一般法人法第333条)
つまり、法的公告を電子公告で行う会社等は、電子公告調査機関に調査を委託しなければならないということです。ただし、決算公告は法定公告にあたりますが、電子公告調査機関による調査対象から外されているので調査の必要はありません。(会社法941条)
*電子公告調査機関とは
電子公告には、官報または日刊新聞紙の場合と違って事後の改ざんが容易であるなどの問題があります。そのため電子公告が適法に行われたか否かに関して客観的証拠を残す必要があり、電子公告の場合は法務大臣の登録を受けた電子公告調査機関の調査を受けなくてはなりません。
電子公告調査機関は、公告期間を通じて定期的にホームページを調査して正常に掲載されているか、改ざんがないか等を調査・判定し、その結果を記録します。そして、電子公告調査機関は電子公告調査の終了後、直ちに調査結果をその電子公告を実施した会社等に通知する義務を負っているのです。
2-4 決算公告に関する特例
すでに説明してきた決算公告を電子公告で行う場合に関する特例をまとめると、以下のような内容になります。
- 決算公告を電子公告で行う場合、他の公告事項と違って電子公告調査機関による電子公告調査を受ける必要がありません。
- 電子公告を公告方法としている会社等が決算公告を実施する場合、要旨による公告は認められず、全文による公告が求められます。
- 決算公告用のホームページは、他の公告事項に関するホームページとはリンクのない別のアドレスを登記できます。
2-5 決算公告だけをホームページで実施する場合
会社等の公告方法を官報または日刊新聞紙による方法としている場合でも、決算公告だけをインターネット上のホームページに掲載できます。(会社法第440条3項、一般法人法第128条第3項,第199条)
なお、この場合は、貸借対照表等が掲載されるウェブページのURLを登記しなければなりません。
3 決算公告を実施するメリットとデメリット
決算公告は株式会社に課せられている義務の1つですが、実施することによってメリットとデメリットが発生するので、事前に把握して上手く対処していくことが求められます。
3-1 決算公告のメリット
決算公告を実施すると知名度の上昇、信頼度の向上、罰則の回避といったメリットが得られます。
①会社名が広く認知される
決算公告を行う公告方法によって一般の人等に認知される度合いは異なりますが、決算公告を実施したほうがしない場合よりもその会社名が広く認知される可能性は高まるでしょう。
日刊新聞紙による決算公告では一般の人が普段から見る媒体なので、利用すればその会社名を多くの人に認知してもらえる機会になるはずです。とくに全国版の日刊新聞紙への掲載の場合、その読者数の多さから相当程度の会社の知名度アップが期待できます。
日本新聞協会広告委員会の「2015年全国メディア接触・評価調査」によると、「新聞を読んでいる人」の割合は77.7%と、「テレビを見ている人」の割合の97.3%に次いで2番目に多くなっています。「インターネット利用している人」の70.4%よりも新聞のほうがまだ多い状況です。
また、一般的な新聞広告への接触状況としては、「新聞広告をみている人」の割合は69.5%と7割近い人が新聞広告を目にしています。決算公告の記事についてどれほど関心をもって見られるかは不明ですが、経営者や会社員などの方への認知は広がるかもしれません。
ほかにも株主や債権者から決算書類の請求があった場合、会社等はそれに応じる義務がありますが、日刊新聞紙に決算公告を掲載しておけば、その対応の負担も軽減できるでしょう。
なお、官報での決算公告の効果は不明ですが、官報は一般の人が日常生活で読む対象にはなりにくいので会社の認知度アップに関する効果は限定的と予想されます。ただし、官報の場合中小企業などが法定公告の方法として登録しているケースが多いため、それらの会社の経営者等には一定の広告効果が期待でき商機の拡大に繋がるかもしれません。
インターネット上の電子公告の場合は、その会社の決算公告や経営状況などを知りたい方が検索して初めて閲覧することになるので、一般の人が偶然に目にする可能性は低いでしょう。ただし、その会社の決算内容を知りたいという方を対象として、決算公告を自社のホームページへの導入のための1つの活用手段として利用することは可能なはずです。
②信頼度の向上
現状では決算公告を実施している企業はごく限られ、大半の会社が違反している中で自社が決算公告を行うことはステークホルダーからの信頼を得ることに繋がるでしょう。つまり、決算公告を戦略的ディスクロージャーの一環として活用するわけです。
ステークホルダーである銀行等の金融機関、仕入先等の取引先や販売先等の顧客などは、取引をもつ会社の経営状態に関する情報を欲しています。例えば、資金や商品等を提供する先として、その会社の財務状況が悪ければ取引を停止したり縮小したりすることも必要になるでしょう。
しかし、逆にその会社が決算公告を行い比較的良好な営業成績や財務状況を公開すれば、取引する事業者は安心して取引を開始したり継続したりできるはずです。また、違反者の多い決算公告を積極的に行っている会社として、ステークホルダーからより大きな信頼を勝ち取れるかもしれません。
③罰則の回避
決算公告を怠ったり、株主等からの決算書類の開示請求を断ったりすると経営者等は罰則を受けることになりますが、決算公告をしておけば当然それが回避できます。
決算公告義務違反に対する罰則の適用は実際には見られませんが、今後も同様の処置が維持されるとは限りません。決算公告義務違反は経営者等の個人に適用される罰則なので、万が一適用されることになればその負担は決して小さなものとは言えないはずです。
会社の経営状態に余裕がでてきたら会社の知名度や信頼度の向上もかねて決算公告を事業推進の手段として活用することも検討するべきでしょう。
3-2 決算公告のデメリット
決算公告を実施すると、手続業務の負荷、広告料、企業情報の開示、などに関するデメリットが生じます。
①手続業務の負荷
決算公告を実施する場合、掲載メディアとの申込みやデータの作成といった業務が発生し、組織に一定の負荷が当然生じます。もちろんこれらの業務は大した手間にはなりませんが、それでも限られた少ない人員で事業活動を遂行している会社にとっては負担に感じられることもあるでしょう。
法定公告であるため規定に則した手続を行い、掲載内容にしていく必要があるため法律等の確認は必須です。そのためとくに初めて決算公告を行う場合には予想外の時間や労力がかかるかもしれません。
②決算公告の広告料
決算公告は、官報、日刊新聞紙と電子公告の3つの手段が利用できますが、広告料などのコストが発生します。
官報の場合、掲載のサイズ等にもよりますが約7.3万円以上の広告料がかかります。日刊新聞紙は各新聞社や掲載サイズにより異なりますが、何十万円、何百万円といった金額になるでしょう。
電子公告の場合は、自社のホームページ等で運用しているサイトを利用すれば、広告料自体は不要です。しかし、別のサーバー運営会社などに依頼して公告すればその費用が発生します。
また、電子公告では他の公告方法のように要旨で掲載することができず、全文での掲載が求められます。そのため、詳細な決算情報を公開したくない場合には電子公告は適しているとはいえないでしょう。
③企業情報の開示
大会社に該当する会社は貸借対照表のみならず損益計算書も掲載しなければなりません。そのためどの程度の資本力でどの程度の儲ける力があるのかなどについて、開示情報から読み取られる可能性が生じます。
財務諸表(=決算書)は会社にとっての競争力や健康状態を計る資料となるため、ライバル会社や顧客などに知られたくないと考えている経営者も少なくないでしょう。また、とくに創業間もない会社などでは、生産や販売が思うように進まず、売上も伸びないような状況が続き会社の経営状況を公開する気になれないというようなケースもあるはずです。
決算情報を開示した場合その情報が分析され、取引や資金提供の判断、競争上の実施手段の策定などに利用され得るため、決算公告を行った会社等は不利益を被ることもあります。
例えば、売上高の大きさ、営業利益率の高さなどからその会社の販売力や価格競争力などを推し量ることも不可能ではありません。ライバル会社などではその情報から競争上優位に立てる価格を決定していくケースもあるでしょう。顧客の場合では値引き交渉の材料としてその財務諸表が利用され、金融機関や投資家などでは資金提供等の判断材料として利用される可能性があります。
このように財務諸表の開示は、その会社にとって不利益になるケースを生じさせることになるかもしれません。
・ 決算公告のメリットとデメリットまとめ
| メリット | 会社名が広く認知される |
|---|---|
| 信頼度が向上する | |
| 罰則を回避できる | |
| デメリット | 手続業務がかさむ |
| 広告料がかかる | |
| 情報開示するリスクが発生する |
4 決算公告の経営上の活用
前に説明した決算公告のメリットとデメリットのほか、自社の経営状況も踏まえて経営に活かすという点から決算公告を検討してみましょう。
4-1 決算公告の活用の意義
決算公告はコストも手間もかかる株式会社等に課せられている義務ですが、顧客、取引先、金融機関などのステークホルダーからの信頼を得るための有効な手段にもなります。そのため会社等として、決算公告を有効に活用していくという行為は経営上間違った選択ではないでしょう。
中小企業などの場合、決算公告をしない会社が大半を占める中で自社が積極的に公告すれば、その信用度を広く公にアピールできます。とくに決算内容が良好な会社の場合は取引先からの信頼度を向上させ、新たな仕入先の拡大を容易にさせるかもしれません。また、顧客にとっても透明性の高い会社との取引は有効であるため、新規取引でのハードルの高さが下がることも期待できるでしょう。
決算公告には一定の費用がかかるというデメリットもありますが、その公告手段を工夫すれば少ない費用でも効果的な公告を実施し経営に活かしていくことも不可能ではありません。
4-2 決算公告の有効な活用法
ここではいくつかの決算公告の有効的な活用方法を紹介しましょう。
①決算公告は官報、その他の法的公告は電子公告で
決算公告を自発的に行いたができるだけ低コストに抑えたい場合は電子公告が最も安くつくでしょう。しかし、その他の法定公告も電子公告にすると電子公告調査機関の調査を受けなくてはならず官報以上のコストが必要になる可能性が生じます。
そのため調査の対象外となっている決算公告は電子公告で、その他の法定公告は官報で行うという選択が有効です。決算公告を官報と定めている場合でも定款を変更すれば可能なので検討してみてはどうでしょうか。
とくにステークホルダーからの要請の多い決算情報の開示をウェブサイトで行っておけば、自社のウェブサイトへのアクセスの増加にも繋がるというメリットも得られます。
②安価な日刊新聞紙を決算公告に利用する
県紙や特定の日刊新聞紙を決算公告に利用すれば、比較的低いコストで高い広告効果も期待できます。
決算公告を企業の広告活動の1つとして利用したい場合では日刊新聞紙の利用が最も効果が高いといるでしょう。しかし、全国版の大手日刊新聞紙を利用する場合、50万円以上の広告料がかかるケースも珍しくないです。そのため、中小企業などの場合そのような広告料を支出することは現実的ではなく、また全国紙に掲載することでの広告効果も得られるとは限りません。
日刊新聞紙を利用する場合、その広告効果を考慮することが重要です。例えば、営業エリアなどが都道府県の単位の一定地域に限定している場合、その地域をカバーするブロック紙や県紙などが最適でしょう。また、工業製品などの原材料、部品や機械などを扱う業界の会社では日刊工業新聞社といった特定分野に強い日刊新聞紙を選択すると他の新聞紙よりも高い広告効果が期待できます。
コスト的にも県紙や日刊工業新聞社の広告料は全国紙に比べ相当程度割安感があるため、有効な媒体といえるでしょう。
③知名度の高い企業情報提供サービス会社等を利用する
全国的に知名度の高い信用情報などの企業情報を提供するサービス会社のウェブサイトを決算公告に利用するのも有効です。
決算公告を電子公告として行う場合、自社のウェブページで実施するケースは多いですが、そのウェブページへのアクセス数が少なければ高い広告効果は期待できません。中小企業などでもSEO対策をしっかりとって検索上位に上がるウェブページを保有していれば広告効果は期待できますが、そうでない場合は別の手立てを検討する必要があります。
その1つとして知名度の高い企業情報提供サービス会社等のウェブサイトの利用が挙げられます。もちろんそのサービス会社等のウェブサイトに決算公告を載せるだけでは広告効果は高いとは言えないでしょう。しかし、企業名の検索サービスや企業情報の提供サービスなどがあるウェブサイトなら、ある程度の広告効果は期待できるのです。
つまり、この活用方法は、アクセスの多いサービス会社等のウェブサイトから自社の決算公告への誘導、そして自社のホームページへの誘導を目指すという活用になります。
4-3 知名度の高い企業情報提供サービスを利用するメリット
そのメリットとしては以下の点が考えられます。
・アクセスの増加
多くの会社やビジネスマンが利用している企業情報提供サービス会社等のウェブサイトなら一般企業のサイトよりも多くのアクセスが見込めます。そのためサービス会社等のウェブサイトに自社の決算公告と企業PR情報を掲載すれば、幅広い企業関係者の目に触れられるというチャンスが増えるわけです。
・サービス会社等のウェブサイトの利用による信頼度アップ
企業情報提供サービス会社等のウェブサイトでは、企業情報、経営に関する各種統計データや分析データなどが用意されていたり、利用できたりします。そのため、多くのビジネスマンがサイトに訪れるなど利用者からの支持の高いサービス会社もみられます。そうしたウェブサイトに決算公告を行うことが自社の信頼度のアップに繋がることもあるでしょう。
・他の広告以上に良好な費用対効果
企業情報提供サービス会社等のウェブサイトへの掲載は、費用的にも官報や日刊新聞紙よりも低コストで済むのでよい費用対効果が望めます。例えば、帝国データバンク社の場合、インターネット決算公告サービス公告掲載・情報登録料は、年間3万円、5年間12万円と設定されています。
・決算公告に加え企業PR掲載といったサービスの併用
決算公告のほか、企業の住所、電話番号、代表者などのプロフィール、PRメッセージ、企業ウェブサイトへのリンクの登録といったサービスを提供しているサービス会社もあります。そうしたサービスを利用できるなら、決算公告と企業のPRを同時に実施することが可能です。また、その登録情報に一般の人が無料でアクセスできるようなサービスもあり、より広範囲の広告効果が望めるでしょう。